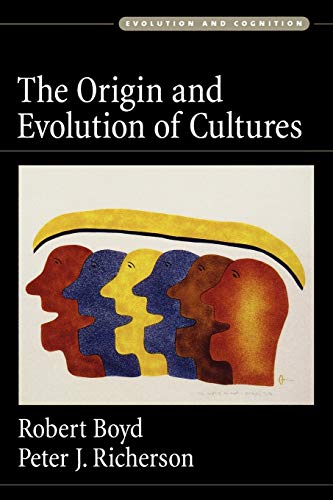間が空いてしまって、まとめるのがおっくうになってるけど頑張ろう。たぶんこの章は本書のひとつの山場です。「ルールに従う」というタイトルの意図を端的に表す「規範同調性」という概念が出てくる章なので。
第6章 自然主義的パースペクティブ
イントロ
標準的な合理的選択理論はホッブズの道具主義の2つの前提を固守している。
- 前提1:実践的推論は帰結主義的
- 前提2:選好は非認知的
しかしこれまで見てきたように、どちらの前提も疑わしいものだ。
このように標準的な合理的選択理論に問題があるとしても、その代替案はまだ明らかでない。
標準的な合理的選択理論とはちがい、道徳哲学者たちは、人々が協力することこそが合理的なのだと考える。でもなぜそうすることが合理的なのかはきちんと説明されていない。だから、なぜ人々が協力するのか、というのをきちんと説明するために、自然主義的パースペクティブから考えてみよう。
6.1 利他主義の謎
自然主義的な意味での利他主義:それを行う生命体にとって不利益となる一方で、他の生命体にとっては利益となる任意の行動(ここで「利益」「不利益」は繁殖適応度で定義される)
自然選択は個体の適応度を促進するが、種の平均適応度を促進するわけではない。利他的な個体の多い種は平均適応度が高いだろう。しかし、利他的な個体は利己的な個体のカモにされる。だから、自然選択は利己的な個体の適応度の方を高めることで、種の平均適応度を下げることになってしまう。
6.2 包括適応度
では、自然選択では利他的行動は淘汰されてしまうのだろうか? そうでもない。
利己的な遺伝子という考え方によると、遺伝子にとっての利益と個体にとっての利益はイコールでない。ある1つの個体の適応度(個体適応度)を減少させる行動でも、その個体の遺伝子コピーが別の個体の中にあるのなら、遺伝子にとっては適応度が増大することはありうる。たとえば、親が自分を犠牲にして子どもを助ければ、親の個体適応度は減少しても、包括的適応度という観点では適応度が増大している。
確かにこうした包括的適応度で利他的行動を説明はできる。でも説明の範囲は限られている。血縁がつながってなければ利他的行動は生まれないだろうし、そもそも血縁と非血縁を区別する方法があるとは限らない。つまり、狭い範囲の利他的行動は説明できても、人間のような「超社会性」をもつ利他的行動を説明するのには不十分なのだ。
6.3 互恵的利他主義
他に、互恵的利他主義という考えで利他主義を説明することもできる。つまり「私の背中を掻いてくれれば、あなたの背中を掻いてあげよう」というやつだ。
包括的適応度の場合、利益を受けるのはその個体の遺伝子コピーだが、互恵的利他主義の場合、その個体自身が利益を受けている。互恵的利他主義によってその個体の個体適応度が上がるのなら、こうした振る舞いは適応的だといえるだろう。
しかしこれは進化的に頑健ではない。というのは、互恵的利他主義者は、初回は協力的に行為して、それに相手がどう反応するか次第で協力したり協力しなかったりを決めるという戦略をとってるから。もしインタラクションが1回限りなら、互恵的利他主義者は「裏切り」によって出し抜かれることになる。つまり、この場合、互恵的利他主義者よりもフリーライダーの方が適応度が高くなる。
互恵的利他主義は、2者間の関係性においてネットワークを維持するのにはそれなりに役立つかもしれない。だけど、集団サイズが大きくなるとフリーライダーが出てくる確率が高まる。そして、1人でもフリーライダーがいればドミノ倒し式に協力関係は崩壊してしまうだろう。だから互恵的利他主義も人間社会にみられるような協力の謎を解くにはぜんぜん役に立たない。
6.4 怪しい仮説のいくつか
だからチンパンジーみたいな人間以外の霊長類の利他主義で人間の利他主義を説明するのには無理があるんだよ。チンパンジーとは別のメカニズムが必要なのだ。だけどなぜか、進化理論家たちはそういうことを認めるのを極端にしぶってきた。
たとえば、人間は知性が高いから協力するのだ、という説明をする人もいる。チンパンジーと人間は本質的に異なるわけではないけれど、人間の方が知性がずっと高いから協力できるのだ、ということだ。だけどこれも説明になってない。だって、知性が高いからこそ協力することもあれば、知性が高いからこそ相手を出し抜くことだってできるのだから。
ボウルズとギンタスは、互恵性に「懲罰」というひねりを加えることで、人間の超社会性を説明しようとする。これは強い互恵性モデルと呼ばれるものだ。逆に、互恵的利他主義の方は弱い互恵性だということになる。
どういうことか?
弱い互恵性モデル(互恵的利他主義)の場合、相手が裏切ったらこちらも裏切るという戦略をとる。この場合、人々が協力するのは相手に裏切られたくないからだ。だけどこれだと、お互い1回しかインタラクションしない関係でなぜ協力が行われるのかを説明できない。現実世界では、1回限りのインタラクションでも人々は協力するものだ。
一方、強い互恵性モデルの場合、人々はデフォルトで協力する。つまり、裏切られるのが怖いから裏切らないのではなく、協力したいから協力する。しかし、相手が裏切ったら相手に懲罰を与える。人々が協力するのはデフォルトなので、これなら1回限りのインタラクションでも人々が協力することを説明できる。
だから、強い互恵性モデルは、人間の超社会性を説明できるモデルの1つの候補になり得るといえる。
ただ、ボウルズとギンタスによる議論の進め方にはちょっと難がある。彼らは、強い互恵性によって人々の協力が実効化されると考える。だけど、彼らが議論を進めるのに使ってるのは最後通牒ゲームの実験結果だ。最後通牒ゲームは協力をテーマとするゲームではない。むしろ、分配の公平性をテーマとするゲームだ。もう少しいうと、最後通牒ゲームは公平性の規範をテーマとしてるのだ。
人々は協力や公平性に直接関心があるわけではない。むしろそれらの根底にある規範に関心があるのだ。だから、われわれが問うべきなのは、人間がどのようにして協力的性向を持つようになったかではなく、人間がどのようにして規範同調者になったかという問題なのだ。
6.5 規範同調性
チンパンジーと人間の子どもでは学習の仕方がぜんぜんちがう。お手本を示されたとき、チンパンジーは効果的なお手本の方を真似する。それに対し人間の子どもは、効果的でないお手本であってもそのまま真似してしまう。
人間の学習は「郷に入っては郷に従え」バイアスを持っている。この場合、利他的行動は文化的パターンとしてずっと頑健なものになる。というのは、互恵的利他主義みたいに、ドミノ倒し式で裏切りが全体に拡大してしまうような事態を防げるからだ。大多数が利他的であれば、その行動をお互い真似することで、全員がそのような行動をとるようになるのだ。
ボウルズとギンタスの主張するような「懲罰」は、こうした同調的模倣の効果を増幅するものだ。懲罰は、「協力」を促すものというよりも、「規範」への同調を促すものなのだ。
生物学的進化が提供するのはこうした規範同調性だ。この性向は、学習能力の向上という点で、個体に利益をもたらすものだ。しかし、この規範同調性によって保証される利他主義は、生物学的パターンではなく、文化的パターンだ。利他主義は生物学的選択圧力の前では脆弱だ。しかし、規範同調性が、利他主義を生物学的選択圧力から遮断してくれるのだ。
しかし、それならなぜ利他主義という文化的パターンは他の文化的パターンよりも頑健なのだろう? おそらくそれは、言語によるものなのではないか。言語があることで、文化的進化のプロセスに意識的誘導の要素を導入することが可能になる。そして、こうした言語の発生を促すのにも、規範同調性は重要な役割を果たしていると考えられる。
6.6 社会生物学に抗して
社会生物学による文化の説明はあまりうまくいっているように思えない。なぜユダヤ人は豚肉を食べないのか? それは、寄生虫に対する防御のための進化的適応だ。だけどこの説明だと、他の文化の人が豚肉を食べていることを説明できない。
進化的枠組みだけだとこうした食のタブーみたいな問題をうまく理解できない。だけど、規範同調性を仮定するとうまく説明できる。つまり、こうした文化的進化は生物的進化とは異なる選択メカニズムに支配されているのだ。
言語の獲得も生物的進化で説明しない方がいい。つまり、「生得的な言語モジュール」みたいなものを仮定する必要はない。脳が自然言語の獲得に適応しているのではなく、自然言語の方が脳に適応できるように文化的に進化したのだ。
6.7 結論
規範同調性を仮定すれば、人間の文化依存性を確立することができて、さらには言語の発生を説明することもできる。そして言語があるからこそ、われわれの実践的知性の根本にある志向的計画システムの起源を説明することができる。
このように、規範同調性が全てのロックされたドアを開ける鍵であるように思われる。われわれはルールに従うことがたまたま好きになった知的生物であるだけではない。ルールに従うことこそ、われわれを、現在あるような知的生物にしたのものなのである。 (p343)
感想
ゲーム理論、認知哲学、言語哲学、とどんどん領域を拡大してきたヒースの闇鍋議論もとうとう進化論の領域にまで拡大した。ただ、議論の流れはすごくわかりやすい。
「集合行為」というのがヒースの思考のベースにあるのだなあ、と改めて思った。包括適応度や互恵的利他主義に基づく利他主義は、フリーライダーに対して脆弱なので人間の超社会性を説明するのに役に立たない。そこで、「規範同調性」という概念を導入することで、フリーライダー問題を解決することで利他主義の頑健性を保証する、という風に議論が進められている。
ただ、この「規範同調性」に議論のすべてがかかっているようにも思えるのが気になる。もし、規範同調性というのが実証的にあまり頑健でない概念だとしたら、この章の議論はぜんぶオジャンになってしまうし、1章~5章までの議論の自然科学的裏づけも不明になってしまう。「規範同調性」だけに絞って1章分まるまる使うくらいの慎重な検討が必要なんじゃないんだろうか。本書では、規範同調性を裏付ける証拠はp324のたった1ページの簡単な紹介だけで終わってしまってる。すごく面白い本なのだけど、一番大事なところで「あれ?」となってしまった。
ヒースが規範同調性の証拠としてあげているのは、チンパンジーと人間の赤ちゃんがお手本をどういう風に学習するかという実験と、あと注に書かれてる別の実験の2つだけなのだけど、もうちょい証拠が必要な気がする。たとえばどちらの実験も赤ちゃんが被験者だけど、大人だったらどうなのかとか、「行為を真似する」ことを「規範に同調する」ことと同一視していいのかとか。元ネタはマイケル・トマセロらしいので、そっちを読めば納得いく説明があるのかな?
あと、なんで人間の場合だと規範同調性が生物進化的に適応的だと言えるのか、というのもよくわからなかった。ヒースは「このことがどのようにして適応的であるのかを理解することは難しくない」(p327)と言っていて、そこに注が振ってあるのだけど、注を見るとリチャーソンとボイドという文化進化論の人の文献が紹介されているだけだ。私にとっては理解することが難しいので一言くらい説明して欲しいのだけど…。それが適応的なのだとしたら、チンパンジーに規範同調性が見られてもおかしくないと思うんだけどなあ。リチャーソン&ボイド文献を読めってことなのかな? 読むか分からんけど、一応リンクを貼っておく。ヒースはこの本の、"Social Learning as an Adaptation"という章を参照してる。でも、文化進化論の専門書って難解な数式がガンガン出てくるらしいので読める自信はない。